「介護福祉士の資格を取得したけど、病院で働くにはどんなスキルが必要なのかな…」
「一般的な介護施設とは違う病院での仕事内容が知りたいけど、情報が少なくて不安…」
これから就職先を検討する上で、病院という選択肢を視野に入れている方は、ぜひ詳しい情報を集めておきましょう。
この記事では、介護福祉士として病院への就職を考えている方に向けて、
- 病院で働く介護福祉士の具体的な仕事内容
- 一般的な介護施設との違いと求められるスキル
- 病院で働くメリットとキャリアパス
上記について、解説しています。
病院という医療現場では介護福祉士にも特有の役割があり、やりがいも大きいものです。
この記事を読めば、病院就職に対する不安が解消され、自分に合った職場選びの参考になるでしょう。
介護福祉士としてのキャリアを考える上で重要な情報をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
好きなところから読む
介護福祉士が病院で働く際の仕事内容

介護福祉士が病院で働く場合、主に入院患者さんの日常生活のサポートが中心的な業務となります。
具体的には、食事介助、入浴介助、排泄介助といった基本的な身体介護から、ベッドメイキングや環境整備、さらには看護師と連携した医療的ケアのサポートまで幅広い業務を担当します。
以下で詳しく解説していきます。
病院という医療現場では、患者さんの治療と回復を最優先に考えた介護が求められるのです。
| 分野 | 主な内容 | 特徴・ポイント |
|---|---|---|
| 身体介護 | 食事・入浴・排泄の介助、体位変換、移乗介助 | ・患者の状態に応じた柔軟な対応 ・褥瘡予防や誤嚥防止などに注意 |
| 環境整備(清掃・シーツ交換) | 病室の清掃、ゴミ処理、ベッドまわりの整理整頓、シーツの交換 | ・感染対策を徹底 ・快適な療養環境づくり ・安全に配慮した作業が必要 |
| 看護師サポート業務 | バイタル測定補助、配膳・下膳、記録補助、処置準備、患者移送 | ・チーム医療の一員として看護師と連携 ・医療行為以外の多様な支援を担う |
| リハビリ支援(回復期) | 移乗・歩行訓練の介助、生活リハビリ、自立支援、家族指導 | ・生活動作の中で機能回復を促す ・過介助を避ける支援 ・退院後を見据えた介護指導も含む |
入院患者の身体介護の役割
介護福祉士が病院で働く場合、入院患者の身体介護が主要な役割となります。
具体的には食事、入浴、排泄の介助が中心的な業務です。
患者さんの状態に合わせた食事介助では、誤嚥を防ぎながら適切な姿勢と速度で食べ物を提供します。
入浴介助では、患者さんの体調や医師の指示を確認した上で、安全に配慮しながら清潔を保つ支援を行います。
「今日は体調が優れないから入浴は遠慮したい…」という患者さんの気持ちに寄り添いながら、清拭や部分浴などの代替方法を提案することも大切な役割です。
排泄介助では、患者さんのプライバシーと尊厳を守りながら、おむつ交換やポータブルトイレの使用をサポートします。
移乗や体位変換の介助も重要な業務で、褥瘡(床ずれ)予防のために定期的に姿勢を変えるよう支援します。
これらの身体介護を通じて、患者さんの日常生活の質を維持し、回復を促進することが病院で働く介護福祉士の大きな役割となっています。
環境整備の一環としての掃除とシーツ交換
病院での環境整備は介護福祉士の重要な役割の一つです。
患者さんが快適に過ごせる環境を整えることで、治療効果の向上や感染予防に貢献します。
環境整備の中心となるのが病室の掃除とシーツ交換です。
毎日の掃除では、床の清掃やゴミ捨て、患者さんの身の回りの整理整頓を行います。
「今日はシーツがよれてしまって寝づらかった…」という患者さんの声を聞くこともあるでしょう。
シーツ交換は単なる清潔保持だけでなく、患者さんの睡眠の質にも直結する大切な業務なのです。
シーツ交換の頻度は病院の方針によって異なりますが、一般的には週に2〜3回、または汚れた場合にはその都度行われます。
特に注意すべき点は以下の通りです。
- 感染対策:患者さんごとに手指消毒を行い、感染症の拡大を防止します。
- 安全への配慮:ベッドからの転落防止など、患者さんの安全に最大限配慮しながら作業を進めます。
- 効率的な作業:他のスタッフと連携し、患者さんの負担を最小限に抑えつつ効率的に行います。
環境整備は地味な業務に思えるかもしれませんが、患者さんの療養環境を整え、回復を支える重要な役割を担っています。
看護師業務のサポート
介護福祉士の病院勤務では、看護師業務のサポートが重要な役割の一つです。
具体的には、バイタルサインの測定補助や検査前の患者さんの準備、配膳・下膳の手伝いなどを担当します。
医療行為はできませんが、看護師の指示のもとで患者さんの状態観察や報告を行い、チーム医療の一員として貢献します。
「看護師さんは忙しそうで声をかけづらいな…」と感じることもあるかもしれませんが、コミュニケーションを大切にすることで円滑な連携が生まれます。
病院では多職種との協働が基本となるため、以下のようなサポート業務が発生します。
- 看護記録の整理補助:患者さんの日常生活の様子や介助内容を記録し、看護師の情報収集をサポートします。
- 処置室や病室の準備:診察や処置がスムーズに行えるよう環境を整えます。
- 患者さんの移送:検査や手術室への移動を安全に介助します。
看護師業務のサポートを通じて、患者さんの治療と回復を間接的に支える役割を果たすことができます。
回復期病院でのリハビリ支援
回復期病院では、介護福祉士はリハビリテーションを支援する重要な役割を担っています。
患者さんの日常生活動作(ADL)の自立を促すため、理学療法士や作業療法士と連携しながら、ベッドから車椅子への移乗や歩行訓練の介助を行います。
「リハビリの時間だけでは十分な回復が見込めない…」と感じる方も多いでしょう。
そこで介護福祉士は、日常生活の中でリハビリの要素を取り入れた「生活リハビリ」を実践します。
例えば食事の際には自分で食べる動作を促したり、着替えの際には麻痺側から衣服を着るよう指導したりと、患者さんの状態に合わせた支援を行います。
また、退院後の生活を見据えた環境調整や家族への介護指導も重要な業務です。
- 生活リハビリの実践:食事、排泄、入浴など日常生活の中でリハビリ効果を高める支援を行います。
- 自立支援:できることは見守りながら、必要な部分だけ介助する「過介助」を避けた関わりを心がけます。
- 家族指導:退院後の生活に向けて、家族に介護方法や住環境の調整について助言します。
回復期病院での介護福祉士の役割は、単なる介護ではなく、患者さんの社会復帰を目指した専門的な支援なのです。
病院勤務と介護施設勤務の違い
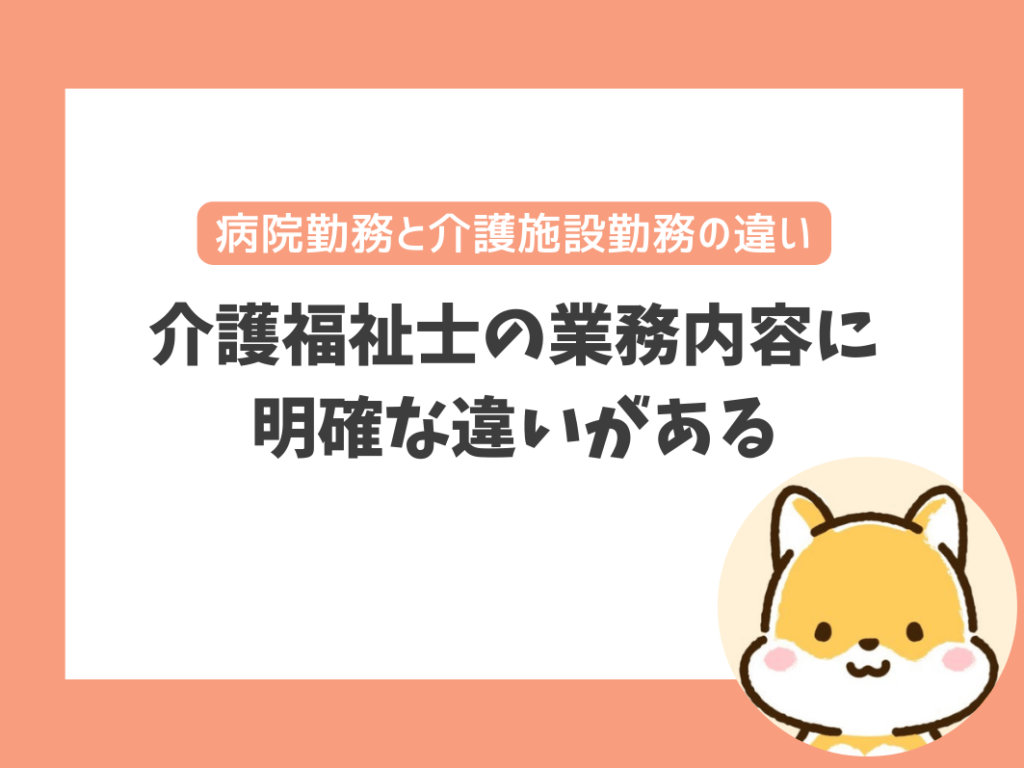
介護福祉士が病院と介護施設で働く場合、業務内容や環境に大きな違いがあります。
例えば、病院では看護師の指示のもと患者の観察や処置の補助を行いますが、介護施設では入浴介助や食事介助など日常生活全般をサポートします。
以下で詳しく解説していきます。
病院では医療行為のサポートが中心となり、介護施設では生活全般の支援が主な役割です。
業務内容の違い
病院と介護施設では、介護福祉士の業務内容に明確な違いがあります。
病院での介護福祉士は主に医療チームの一員として、看護師の指示のもとで働くことが特徴です。
具体的な業務としては、入院患者の食事・排泄・入浴などの日常生活援助が中心となります。
また、医療処置の補助や観察も重要な役割です。
バイタルチェックや患者の状態変化の報告など、医療スタッフとの連携が求められます。
「病院は医療行為が中心だから、介護の仕事は少ないのでは?」と思われるかもしれません。
しかし実際には、入院患者の生活を支える重要な役割を担っています。
一方、介護施設では介護福祉士がケアの中心的存在となり、より幅広い業務と責任を持ちます。
施設では、ケアプランの作成や家族との連絡調整など、マネジメント業務も担当することが多いでしょう。
また、レクリエーションの企画・実施なども介護施設特有の業務といえます。
病院では医療的ケアが優先されるため、生活の質向上に関わる活動は比較的少ない傾向にあります。
病院勤務の介護福祉士は医療知識が求められる一方、介護施設では生活支援のスキルがより重視されます。
業務内容の違いを理解することで、自分に合った職場環境を選ぶ判断材料になるでしょう。
職場環境の違い
病院と介護施設では、職場環境に大きな違いがあります。
病院は医療を中心とした環境で、清潔感と緊張感が漂っています。
常に医師や看護師との連携が求められ、チーム医療の一員として働く意識が必要です。
「病院は思っていたより忙しくて大変かも…」と感じる方もいるでしょう。
一方、介護施設は生活の場としての雰囲気があり、比較的ゆったりとした時間が流れています。
病院では急性期から回復期まで様々な状態の患者さんと関わるため、対応の幅広さが求められます。
また、病院は24時間体制のため、夜勤や交代制勤務が一般的です。
介護施設と比べて医療機器や設備が充実しており、最新の医療知識に触れる機会も多いでしょう。
職員の数も病院の方が多く、大規模な組織の中で働くことになります。
病院勤務を選ぶ際は、このような環境の違いを理解しておくことが重要です。
>社会福祉士の就職先はどこ?資格が活かせる一般企業・フリーランス・公務員でランキング
病院勤務の介護福祉士の一日の流れ
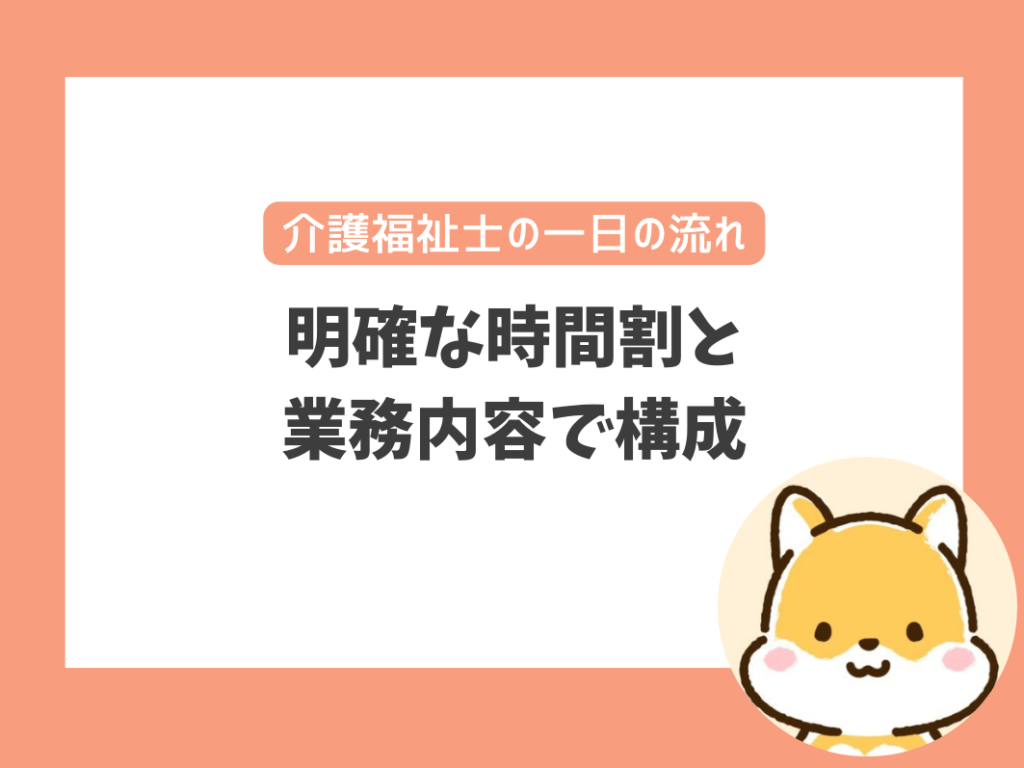
病院勤務の介護福祉士の一日は、明確な時間割と業務内容で構成されています。
朝は申し送りから始まり、患者さんの状態確認や朝食介助、清潔ケアへと移行します。
午前中は入浴介助やリハビリ補助、環境整備などを行い、午後からは排泄介助やレクリエーション、記録作成などの業務をこなします。
夕方には夕食介助や就寝準備を担当し、夜勤帯では定期的な巡回や緊急対応に備えます。
病院という医療現場では、常に医師や看護師と連携しながら、患者さんの回復を支援する重要な役割を担っているのです。
介護福祉士が病院で働くメリット
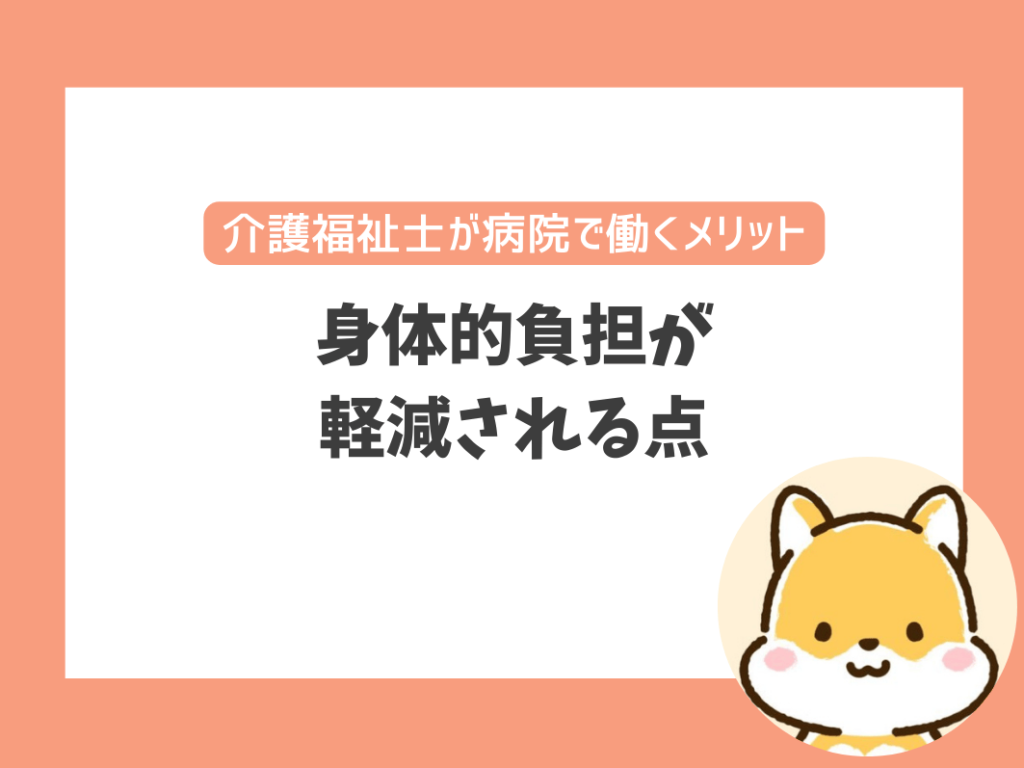
介護福祉士が病院で働く最大のメリットは、介護施設と比較して身体的負担が軽減される点です。
例えば、入浴介助や移乗介助などの身体的負担の大きい作業も、リフトなどの福祉機器が充実していたり、複数のスタッフで対応できたりするケースが多いでしょう。
以下で詳しく解説していきます。
病院では多職種連携が充実しており、看護師や医師との協力体制が整っているため、一人で抱え込む業務が少なくなります。
た表を作成しました:
| 観点 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 身体的負担の軽減 | 福祉機器の充実、短期入院、チーム連携による負担分散 | ・腰痛リスクの低下 ・介助が比較的軽め ・長く働きやすい環境 |
| 医療知識の習得 | 医療スタッフとの連携、疾患理解、急変対応やバイタル観察の経験 | ・現場で学べる医療的視点 ・転職やキャリアアップに有利 ・介護の質向上に直結 |
| 患者の回復を見守るやりがい | リハビリ支援、ADL向上のサポート、感謝される喜び | ・成長や変化を実感できる ・モチベーション向上 ・人の人生に深く関われる誇り |
| 多様な年齢層との交流 | 若年層〜高齢者まで幅広い患者と関わる | ・コミュニケーション力向上 ・視野が広がる ・人間関係のバリエーションが豊富 |
身体的負担が軽減される
病院勤務の介護福祉士は、介護施設と比較して身体的負担が軽減される大きなメリットがあります。
まず、病院では患者の移乗や体位変換をする際に、電動ベッドやリフトなどの福祉機器が充実しています。
また、急性期病院では入院期間が短いため、長期的な介護による腰痛リスクが低減されるでしょう。
「毎日の業務で腰を痛めるのではないか…」と不安に思っている方も多いはずです。
病院では看護師や医師など多職種と連携して業務を行うため、一人で抱え込む状況が少なく、身体的な負担が分散されます。
さらに、病院では医療的ケアが中心となるため、食事介助や入浴介助などの重労働が介護施設ほど多くない傾向にあります。
特に回復期リハビリテーション病棟では、患者の自立支援が目標となるため、見守りや声かけが中心となり、直接的な身体介助が減少します。
このように、病院勤務は身体への負担が比較的軽く、長く働き続けられる環境といえるでしょう。
医療知識の習得が可能
病院勤務の介護福祉士は、医療現場で働くことで医療知識を自然と習得できる大きなメリットがあります。
日々の業務を通じて、様々な疾患や症状について学ぶ機会が豊富にあるでしょう。
「医療用語がわからなくて困っていたけど、病院で働くうちに少しずつ理解できるようになった…」と感じる方も多いはずです。
看護師や医師との連携の中で、医療処置の基礎知識や観察ポイントを習得できます。
バイタルサインの見方や異常の早期発見など、医療的視点を身につけられるのは大きな強みとなります。
また、急変時の対応や医療機器の基本的な取り扱いなど、介護施設では学びにくい知識を得られることも魅力です。
この医療知識は、キャリアアップや転職時にも大きなアドバンテージとなるでしょう。
さらに、患者さんへのより適切なケアにつながり、介護の質を高める効果もあります。
医療と介護の両方の視点を持つことで、より総合的な支援ができるようになるのです。
患者の回復を見守るやりがい
病院で働く介護福祉士の大きなやりがいは、患者さんの回復過程に寄り添えることです。
入院時に自力での生活が困難だった患者さんが、日々のケアやリハビリを通じて少しずつ回復していく姿を間近で見守れるのは、何物にも代えがたい喜びとなります。
「あの時は全く動けなかった患者さんが、今は自分で食事ができるようになった…」そんな瞬間に立ち会えることは、介護福祉士としての誇りを感じられる瞬間でしょう。
特に回復期リハビリテーション病棟では、患者さんの回復が目に見えやすく、自分のケアが直接患者さんの生活機能改善につながる実感を得やすい環境です。
退院時に「ありがとう」と笑顔で言われる瞬間は、すべての苦労が報われる瞬間となります。
患者さんの小さな変化に気づき、その成長を医療チームと共有できることも、病院勤務ならではの醍醐味といえるでしょう。
多様な年齢層との交流
病院での介護福祉士の仕事は、多様な年齢層の患者さんとの交流が大きな特徴です。
高齢者だけでなく、若年層や中年層まで幅広い世代と関わる機会があります。
この環境は、介護施設とは異なる人間関係の構築を経験できる貴重な場となるでしょう。
「同じ高齢者ばかりの環境に少し疲れてきた…」と感じている方にとって、病院勤務は新鮮な刺激となることが多いものです。
様々な背景を持つ患者さんとの会話から、人生観が広がることも魅力の一つ。
若い患者さんからは最新のトレンドを教えてもらったり、中年層の方からは仕事の話を聞いたりと、自分自身の視野を広げられます。
また、多様な年齢層と接することで、コミュニケーション能力も自然と向上していきます。
幅広い世代に対応できる柔軟性は、介護福祉士としてのスキルアップにも繋がる重要な要素となっています。
介護福祉士が病院で働くデメリット
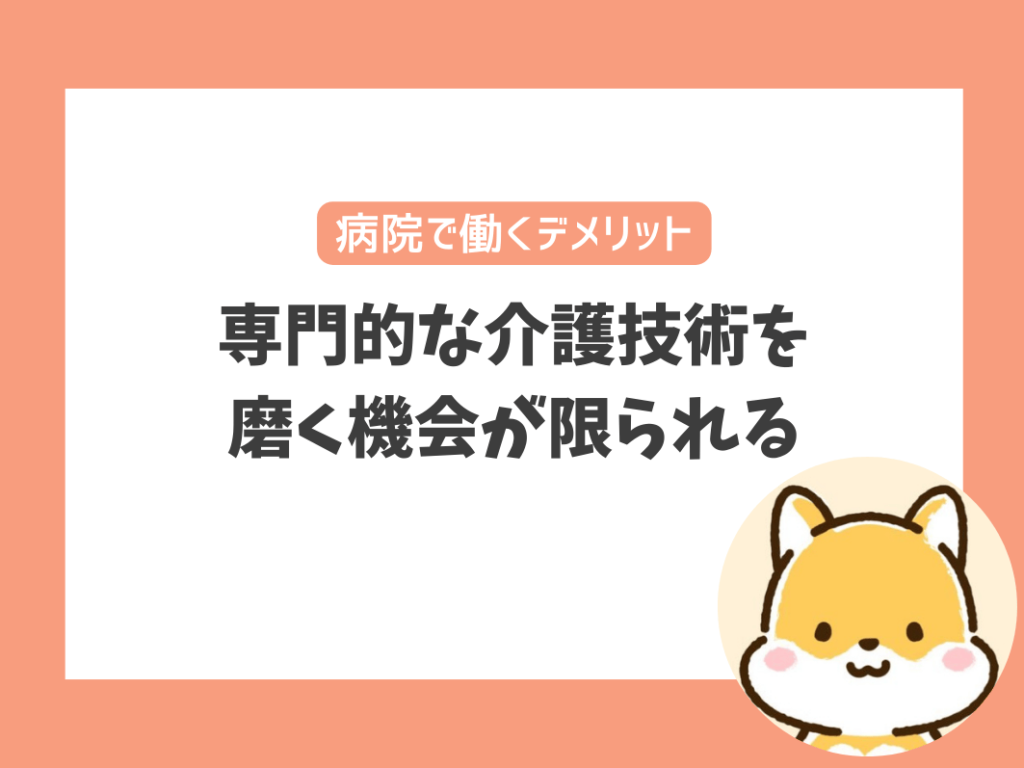
介護福祉士が病院で働く場合、いくつかの課題に直面することも事実です。
医療現場では、看護師や医師との連携が必須ですが、専門性の違いから意思疎通に苦労することがあります。
例えば、医療用語の理解不足や役割分担の曖昧さから、チーム医療がスムーズに進まないケースも少なくありません。
また、介護施設と比較すると、専門的な介護技術を磨く機会が限られることもデメリットの一つでしょう。
病院では医療行為が中心となるため、介護福祉士としての専門性を発揮しづらい環境に戸惑うこともあるかもしれません。
さらに、理想とする介護と医療現場の現実とのギャップに悩む介護福祉士も多いのが現状です。
加えて、病院環境では様々な感染症リスクにさらされる可能性が高く、常に感染対策への意識が求められます。
| 課題 | 内容 | 解決策・対策 |
|---|---|---|
| 医療スタッフとの関係構築の難しさ | 他職種との連携が必須、職種間の壁やコミュニケーションギャップ | ・積極的なコミュニケーション ・医療知識の習得 ・自分の専門性をアピール |
| スキルアップの機会が限られる | 医療行為は看護師の業務、介護福祉士の昇進ルートが限定的 | ・自己研鑽を積む ・研修機会や資格取得支援がある病院を選ぶ |
| 理想と現実のギャップ | 患者との時間不足や業務の多忙さ、専門職としての役割が限定される場合がある | ・自分の役割を明確にし、コミュニケーションを大切にする ・職場環境を事前に調査 |
| 感染リスクの存在 | 医療現場特有の感染リスク、感染症対策が必要 | ・手洗いや消毒、マスク着用など徹底した感染対策 ・定期的な健康チェックや予防接種 |
医療スタッフとの関係構築の難しさ
病院での介護福祉士は、医療チームの一員として働くため、他職種との関係構築が課題となります。
看護師や医師など医療専門職との連携が必須ですが、職種間の壁を感じることも少なくありません。
「自分の意見が尊重されないのではないか…」と不安に思う方もいるでしょう。
特に医療現場では、介護福祉士の立場や役割が明確に理解されていないケースもあります。
医療用語や専門知識の差から、コミュニケーションギャップが生じることもあるのが現実です。
また、病院によっては介護福祉士の配置人数が少なく、孤立感を抱きやすい環境もあります。
この課題を克服するには、以下の取り組みが効果的です。
- 積極的なコミュニケーション:日々の申し送りや会議に積極的に参加し、患者情報を共有することで信頼関係を構築できます。
- 医療知識の習得:基本的な医療知識を学ぶことで、他職種とのコミュニケーションがスムーズになります。
- 自分の専門性をアピール:介護の専門家としての視点や気づきを伝えることで、チーム内での存在価値を高められます。
医療チームの一員として認められるには時間がかかりますが、互いの専門性を尊重する関係づくりが重要です。
スキルアップの機会が限られる
病院勤務の介護福祉士は、施設と比較してスキルアップの機会が限られる場合があります。
病院では医療行為は看護師の業務領域となるため、介護福祉士が医療的なスキルを習得する公式な機会は少ないでしょう。
「もっと専門的な知識を身につけたいのに、なかなか機会がない…」と感じる方も多いはずです。
特に急性期病院では、患者の入れ替わりが早く、長期的な関わりを通じた介護技術の向上が難しい環境といえます。
また、キャリアパスが明確でないことも課題の一つです。
施設では主任やリーダーなどのステップアップが見えやすいのに対し、病院では介護職の昇進ルートが限定的な場合が多いのが現状です。
自己研鑽の機会も、病院の方針や規模によって大きく異なります。
- 研修機会の少なさ:大規模病院では看護師向けの研修は充実していても、介護職向けの専門研修が少ないケースがあります。
- 資格取得支援の限定:介護福祉士としての上位資格取得に対する支援体制が整っていない病院も少なくありません。
このような環境では、自ら積極的に学ぶ姿勢が特に重要になってきます。
病院勤務を選ぶ際は、スキルアップの機会がどの程度あるのかを事前に確認しておくことが大切です。
理想と現実のギャップ
病院で働く介護福祉士には、医療現場ならではの理想と現実のギャップが存在します。
多くの介護福祉士は「患者さんとじっくり関わりたい」という理想を持って病院に就職しますが、実際は業務の多忙さから十分な時間が取れないことがあります。
「もっと患者さんと話す時間があればいいのに…」と感じることも少なくないでしょう。
医療現場では、介護よりも治療が優先されるため、介護福祉士の専門性を十分に発揮できない場面も存在します。
また、病院によっては介護福祉士の業務が雑務中心になってしまい、専門職としての役割が限定されることもあります。
医療チームの中での立ち位置が曖昧で、看護助手との業務区分が不明確な職場環境も少なくありません。
理想と現実のギャップを埋めるには、自分の役割を明確にし、チーム内でのコミュニケーションを大切にすることが重要です。
病院で働く前に、実際の業務内容や職場環境について詳しく調査しておくことで、ギャップによるストレスを軽減できます。
理想と現実のギャップは存在しますが、それを理解した上で自分の強みを活かせる職場を選ぶことが、病院勤務を成功させる鍵となります。
感染リスクの存在
病院で働く介護福祉士は、医療現場特有の感染リスクに常に向き合っています。
患者の中には感染症を持つ方も多く、日常的な介護業務を通じて感染するリスクが存在するのです。
「自分も感染してしまったらどうしよう…」と不安に感じる方もいるでしょう。
特に新型コロナウイルスの流行以降、医療現場での感染対策はより厳格になりました。
病院では感染症対策として、手洗い・消毒・マスク着用・防護服の着用など、様々な予防措置が徹底されています。
これらの対策は患者だけでなく、スタッフ自身を守るためにも欠かせません。
また、定期的な健康チェックや予防接種の実施も、病院勤務の介護福祉士には求められることが多いでしょう。
感染対策の知識と技術を身につけることは、病院で働く介護福祉士にとって必須のスキルとなっています。
適切な予防策を講じることで、リスクを最小限に抑えながら安全に業務を遂行することが可能です。
感染リスクは確かに存在しますが、正しい知識と対策によって管理できるものだと理解しておきましょう。
病院で働く介護福祉士の特徴を知る
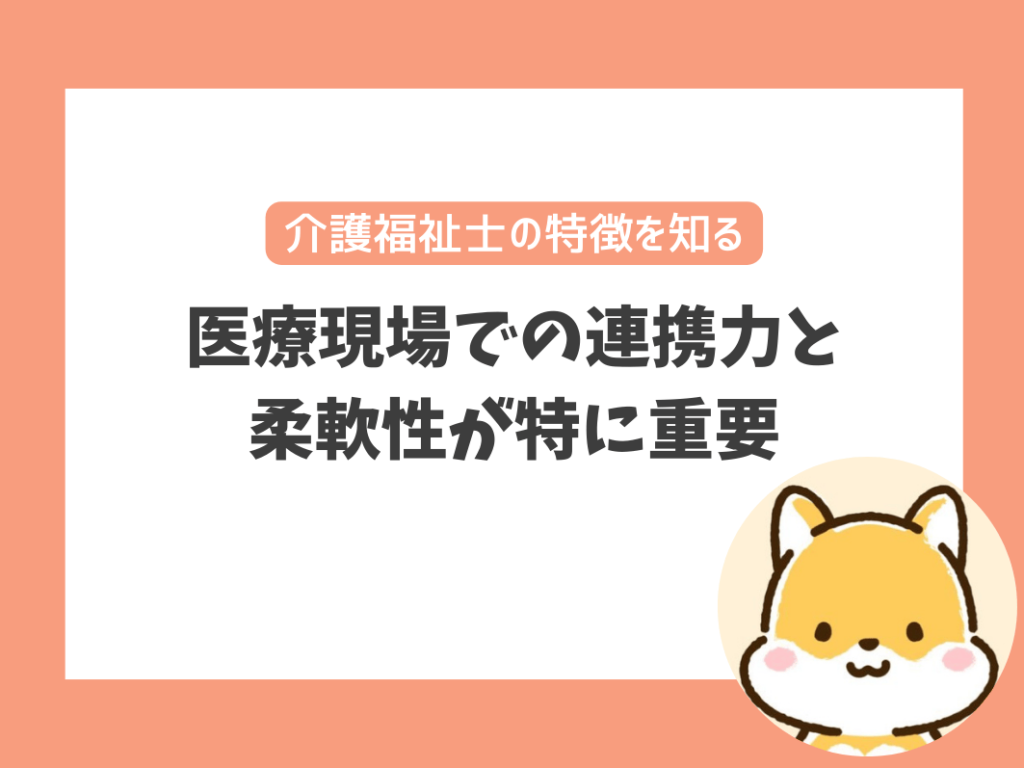
病院で働く介護福祉士には、いくつかの特徴的な資質が求められます。
医療現場での連携力と柔軟性が特に重要です。
以下で詳しく解説していきます。
医師や看護師との円滑なコミュニケーションを取りながら、患者さんの状態変化に対応できる冷静さが必要となるでしょう。
転職を考える際のポイント
病院への転職を考える介護福祉士は、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが大切です。
まず第一に、自分の希望する診療科や病棟タイプを明確にしましょう。
回復期リハビリテーション病棟では介護福祉士の専門性を活かせる機会が多い傾向があります。
「自分はどんな患者さんのケアに携わりたいのだろう…」と具体的にイメージすることが転職成功の第一歩です。
次に、病院の介護体制や介護福祉士の位置づけを確認することが重要です。
病院によって介護福祉士の業務範囲や責任は大きく異なります。
面接時には具体的な業務内容や教育体制について質問しておくと良いでしょう。
また、夜勤の有無やシフト体制も確認すべきポイントです。
病院は24時間体制のため、自分のライフスタイルに合った勤務形態かどうか検討する必要があります。
さらに、給与体系や昇給制度についても事前に調査しておくことをお勧めします。
病院では資格手当や夜勤手当など、基本給以外の収入源も確認しておくと良いでしょう。
最後に、実際に働いている介護福祉士の声を聞くことができれば、より具体的なイメージを持つことができます。
転職サイトの口コミや知人の紹介など、リアルな情報収集を心がけましょう。
病院選びの基準
病院選びの基準で最も重要なのは、自分のキャリアビジョンに合った医療機関を選ぶことです。
まず、病院の種類(急性期・回復期・慢性期)によって業務内容が大きく異なります。
急性期病院では医療行為のサポートが多く、回復期ではリハビリ支援、慢性期では生活援助が中心となるでしょう。
「自分はどんな介護に携わりたいのか」という点を明確にしておくことが大切です。
次に、病院の規模も重要な判断材料になります。
大規模病院では専門性の高い医療知識を習得できる一方、中小規模の病院では幅広い業務を経験できる可能性があります。
また、教育体制が整っているかどうかも確認しましょう。
介護福祉士としてのスキルアップを目指すなら、研修制度や資格取得支援が充実している病院を選ぶと良いでしょう。
「キャリアアップしたいけど、研修の機会が少ないかも…」と不安に感じる方は、面接時に教育制度について質問することをおすすめします。
通勤時間や勤務シフトなど、ワークライフバランスに関わる条件も忘れずに確認しておくべきポイントです。
病院選びは単なる就職先の選択ではなく、あなたの介護福祉士としてのキャリア形成に大きく影響する重要な決断なのです。
病院への転職でおすすめの転職サイトは「マイナビ介護職」
病院への転職を目指す際に特におすすめの転職エージェントを厳選しました。
マイナビ介護職|大手だからこそ高収入求人も多数

「マイナビ介護職」は大手人材会社の「マイナビ」が運営するサービスで、大手だからこその求人をトップクラスで保有しています。
マイナビ介護職では資格がなくても利用できますが、以下の資格を保持していることでよりあなたの条件にぴったりのお仕事を見つけることができるでしょう。
はじめての転職にも強い転職サイトで、以下の方におすすめです。
※株式会社マイナビのプロモーションを含みます
転職相談は完全無料で、24時間いつでもWEBから登録が可能となっているため、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
利用料は完全無料で、24時間いつでもWEBから登録が可能です。
介護福祉士の病院勤務に関するQ&A
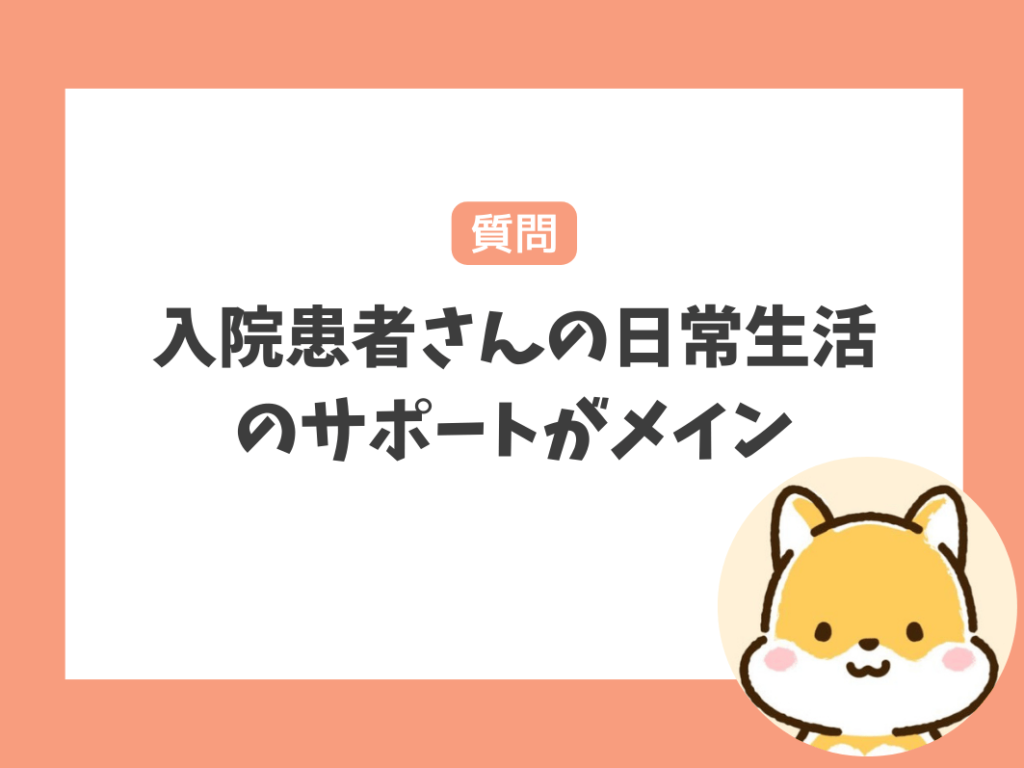
介護福祉士が病院で働く際の疑問や不安を解消するために、よくある質問とその回答をまとめました。
以下で詳しく解説していきます。
転職や就職を検討する際には、具体的な仕事内容や待遇について事前に知っておくことが重要です。
病院での介護福祉士の役割は?
病院での介護福祉士の主な役割は、入院患者さんの日常生活のサポートです。
具体的には、食事・入浴・排泄などの身体介護を中心に、ベッドメイキングや環境整備も担当します。
また、患者さんの移動介助や体位変換、リハビリテーションの補助なども重要な業務となります。
「病院内で看護師と仕事が被るのでは?」と疑問に思う方もいるでしょう。
実際には、看護師は医療行為や処置を担当し、介護福祉士は生活支援に専念するという役割分担が明確です。
特に回復期リハビリテーション病棟では、患者さんの自立支援に向けた介助技術が求められます。
病院によっては、レクリエーションの企画・運営や退院支援計画への参加など、業務範囲が広がることもあります。
医療チームの一員として、患者さんの状態変化を観察し、適切に報告する役割も担っています。
病院勤務の給料はどのくらい?
介護福祉士の病院勤務における給与水準は、一般的に月給20万円~25万円程度です。
この金額は施設の規模や地域、経験年数によって変動します。
大学病院や総合病院などの大規模医療機関では、比較的高い給与が期待できるでしょう。
「病院は夜勤手当が充実しているから給料が良いのでは?」と考える方もいるかもしれません。
確かに、夜勤がある場合は一回あたり5,000円~10,000円程度の手当が付くことが多いです。
また、病院勤務の介護福祉士は、以下のような手当が基本給に加算されることがあります。
- 資格手当:介護福祉士資格に対して月5,000円~10,000円程度
- 処遇改善手当:介護職員処遇改善加算として月額1万円~3万円程度
- 住宅手当:条件により月5,000円~2万円程度
公立病院や大学病院などの公的機関では、昇給やボーナスの制度が整っていることも多いため、長期的なキャリアを考えると安定した収入が見込めます。
民間病院と比較すると、公的機関の方が福利厚生が充実している傾向にあります。
病院での介護福祉士の給与は、介護施設と比べて若干高めの傾向がありますが、勤務条件や責任の重さも考慮する必要があるでしょう。
介護福祉士の求人情報はどこで探す?
介護福祉士の求人情報は、複数の情報源から効率的に探すことができます。
最も一般的なのは、ハローワーク(公共職業安定所)での求人検索です。
専門的な介護求人サイトも充実しており、「カイゴジョブ」「きらケア」「カイゴWORKER」などが人気を集めています。
これらのサイトでは、病院勤務に特化した検索も可能です。
「病院で働きたいけど、どこから情報を集めればいいのか分からない…」と悩んでいる方も多いでしょう。
地域の病院のホームページも、直接募集情報を掲載していることがあります。
介護福祉士養成校の就職支援窓口も活用できる重要な情報源です。
転職エージェントを利用すれば、非公開求人や条件交渉のサポートも受けられます。
複数の情報源を併用することで、自分に合った病院求人を見つける可能性が高まります。
まとめ:介護福祉士の病院での役割と魅力
今回は、介護福祉士として病院で働くことに興味がある方に向けて、
- 病院で働く介護福祉士の具体的な仕事内容
- 病院での介護福祉士の役割と求められるスキル
- 介護福祉士が病院で働くメリットと注意点
介護福祉士が病院で働く場合、医療チームの一員として患者さんの生活支援を担う重要な役割があります。
上記について、解説してきました。
日常生活の介助だけでなく、リハビリテーションの補助や退院支援など、幅広い業務に携わることができるでしょう。
これまで培ってきた介護の知識や技術は、病院という環境でも十分に活かすことができます。
病院で働く介護福祉士は、医療知識を深められる点や安定した労働環境が得られる点など、キャリア形成において大きなメリットがあるはずです。
もちろん、医療現場特有の緊張感や責任の重さはありますが、それ以上に患者さんの回復を間近で支援できる喜びは大きいでしょう。
ぜひ自分の適性や希望に合わせて、病院での介護福祉士としての道を検討してみてください。
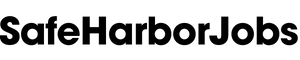

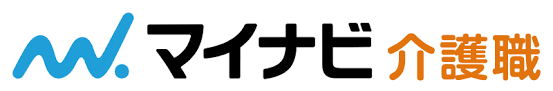

 レバウェル
レバウェル ブレイブ介護士
ブレイブ介護士 スタッフサービス・メディカル
スタッフサービス・メディカル レバウェル介護
レバウェル介護 ジョブメドレー
ジョブメドレー 介護ワーカー
介護ワーカー