「介護福祉士の資格を取得したけど、どんな場所で働けるのかな?」
「特別養護老人ホーム以外にも活躍できる場所があるのか知りたい…」
介護福祉士は国家資格であり、その専門性を活かして働ける場所は実は多岐にわたります。
この記事では、介護の仕事に興味がある方や資格取得を目指している方に向けて、
- 介護福祉士が働ける施設やサービスの種類
- それぞれの職場の特徴や求められるスキル
- 介護福祉士として働く際の給与や待遇の違い
上記について、解説しています。
介護の現場は多様化しており、あなたの希望やライフスタイルに合った働き方を選ぶことができるのが魅力です。
これから介護福祉士として一歩を踏み出そうとしている方も、すでに資格を持っていて転職を考えている方も、ぜひ参考にしてください。
好きなところから読む
介護福祉士が働ける主な場所
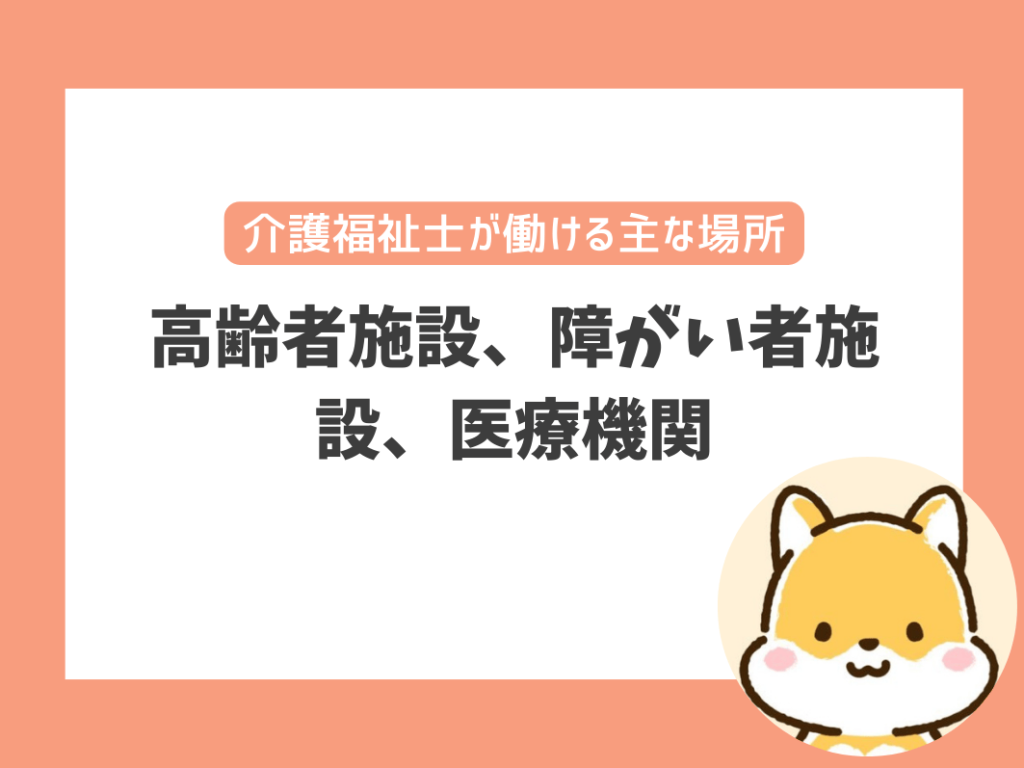
介護福祉士が働ける主な場所は、高齢者施設から障がい者施設、医療機関まで多岐にわたります。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、有料老人ホーム、訪問介護、デイサービス、グループホーム、障がい者施設、病院など、それぞれの場所で異なる役割を担っています。
以下で詳しく解説していきます。
介護福祉士は専門的な知識と技術を持つ国家資格者として、様々な現場で必要とされています。
| 施設 | 役割・業務内容 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 食事、入浴、排泄介助。日常生活支援とチームケア、介護記録作成。 |
| 介護老人保健施設 | リハビリ補助、医療ケア支援、家族への介護指導、退所後の生活環境調整。 |
| 介護付き有料老人ホーム | 食事、入浴、排泄介助、レクリエーション、服薬管理、ターミナルケア支援。 |
| 訪問介護事業所 | 身体介護、生活援助、相談・助言、一対一での個別ケア、利用者との深い信頼関係構築。 |
| デイサービス | 送迎、入浴介助、レクリエーション、生活支援、利用者の生活リズム調整。 |
| グループホーム | 食事準備・介助、入浴・排泄介助、レクリエーション、認知症ケア、家庭的支援。 |
| 障がい者施設 | 日常生活支援、社会参加支援、コミュニケーション支援、生活訓練。 |
| 病院 | 食事、入浴、排泄介助、移動・移乗支援、医療ケア支援、退院支援、リハビリ補助。 |
特別養護老人ホームでの役割
特別養護老人ホーム(特養)は、介護福祉士が最も多く活躍する職場の一つです。
ここでは、常時介護が必要な要介護3以上の高齢者に対して、24時間体制での生活支援を行います。
特養での介護福祉士の主な役割は、入居者の日常生活全般のサポートです。
具体的には以下のような業務を担当します。
- 食事介助:入居者一人ひとりの咀嚼・嚥下機能に合わせた食事提供と、安全な食事介助を行います。
- 入浴介助:身体状況に配慮しながら、プライバシーを守った丁寧な入浴支援を提供します。
- 排泄介助:尊厳を守りながら、個々の状態に合わせた排泄ケアを実施します。
- 移動・移乗介助:安全な移動をサポートし、褥瘡予防にも配慮します。
「特養は体力的にきつそう…」と不安に思う方もいるでしょう。
確かに身体介護が中心となりますが、最近は介護機器の導入も進み、身体的負担の軽減が図られています。
また、特養では介護記録の作成やケアカンファレンスへの参加など、チームケアの一員としての役割も重要です。
多職種と連携しながら、入居者一人ひとりの生活の質を高めるための支援を行います。
特別養護老人ホームは安定した雇用環境が整っていることが多く、介護福祉士としてのキャリアを築く基盤となる職場といえるでしょう。
介護老人保健施設での業務
介護老人保健施設(老健)は、医療ケアと生活支援のバランスが取れた施設です。
ここで働く介護福祉士は、リハビリテーションを受けながら在宅復帰を目指す利用者の支援を主な業務としています。
具体的な業務内容には、食事・入浴・排泄などの日常生活の介助に加え、機能訓練指導員と連携したリハビリ補助があります。
「このままリハビリを続けて自宅に戻れるだろうか…」と不安を抱える利用者の気持ちに寄り添いながら、自立支援を促すことが重要な役割です。
老健では医療的ケアも行うため、看護師との連携が密接であり、医療知識を活かした観察力が求められます。
また、在宅復帰を目指すため、家族への介護指導や退所後の生活環境調整にも関わることがあります。
介護記録の作成や多職種とのカンファレンス参加も重要な業務の一つです。
老健での介護福祉士は、医療と介護の架け橋となり、利用者の在宅復帰という目標達成をサポートする専門職として活躍しています。
介護付き有料老人ホームの仕事内容
介護付き有料老人ホームでは、介護福祉士は入居者の日常生活全般をサポートする重要な役割を担っています。
主な業務は食事・入浴・排泄などの身体介助から始まり、レクリエーションの企画・実施、服薬管理のサポート、生活相談など多岐にわたります。
「24時間体制で働くのは大変そう…」と思われるかもしれませんが、シフト制で働くため、自分のライフスタイルに合わせた働き方も可能です。
介護付き有料老人ホームの特徴は、比較的自立度の高い方から介護度の高い方まで幅広く対応している点です。
入居者一人ひとりの状態に合わせたケアプランを作成し、それに基づいた介護サービスを提供します。
また、医療機関との連携も重要な業務の一つで、看護師と協力しながら入居者の健康管理をサポートします。
施設によっては、ターミナルケア(終末期ケア)まで行うところもあり、人生の最期まで寄り添う深い関わりを持つことができます。
介護付き有料老人ホームでの介護福祉士の仕事は、入居者の尊厳を守りながら、その人らしい生活を支える専門性の高い仕事といえるでしょう。
訪問介護事業所での働き方
訪問介護事業所では、利用者の自宅を訪問して直接介護サービスを提供します。
この働き方の最大の特徴は、施設内勤務とは異なり、利用者の生活環境に合わせた個別ケアを実践できる点です。
訪問介護における介護福祉士の主な業務内容には以下のようなものがあります。
- 身体介護:入浴、排泄、食事、着替えなど日常生活における基本的な介助を行います。
- 生活援助:調理、洗濯、掃除、買い物など家事全般のサポートを提供します。
- 相談・助言:利用者や家族からの相談に応じ、適切な生活アドバイスを行います。
「一人で判断しなければならない場面が多いので不安…」と感じる方もいるでしょう。
しかし、訪問介護では利用者との一対一の関係性を築けるため、深い信頼関係を構築できるメリットがあります。
また、施設とは異なり、時間に追われることなく利用者と向き合えることも魅力の一つです。
シフト制で働くことが多く、ワークライフバランスを重視したい介護福祉士にとって選択肢となるでしょう。
訪問介護の仕事は、自立支援の観点から利用者の残存能力を活かしながら、その人らしい生活を支える重要な役割を担っています。
デイサービスでの活動内容
デイサービスは、日中のみ介護サービスを提供する通所介護施設です。
介護福祉士はここで、利用者の日常生活全般をサポートする重要な役割を担っています。
朝の送迎から始まり、バイタルチェックや入浴介助、食事介助、レクリエーション活動の企画・実施まで幅広い業務に携わります。
「毎日同じ顔ぶれの利用者さんと関わりたい」という方には、デイサービスは理想的な職場かもしれません。
デイサービスの大きな特徴は、利用者が自宅と施設を行き来するため、在宅生活の継続を支援できる点です。
利用者の生活リズムを整え、家族の介護負担を軽減する役割も果たしています。
業務内容は施設によって異なりますが、一般的には以下のような活動を行います。
- 送迎業務:利用者の自宅と施設間の送迎を行い、乗降の際の安全確保も担当します。
- 入浴介助:身体状況に合わせた入浴方法で、安全かつ快適な入浴をサポートします。
- レクリエーション活動:体操や手芸、ゲームなど、利用者の心身機能維持・向上につながる活動を企画・実施します。
- 食事介助:利用者の嚥下状態に合わせた食事提供と、必要に応じた介助を行います。
デイサービスでは、利用者一人ひとりの状態や変化を観察し、適切なケアを提供する観察力も求められます。
他の職種と連携しながら、利用者の在宅生活継続を支援するのがデイサービスでの介護福祉士の重要な役割です。
グループホームでの支援
グループホームは認知症高齢者を対象とした少人数の共同生活の場で、介護福祉士はここで重要な役割を担っています。
グループホームでは、入居者5〜9名に対して職員が24時間体制でケアを提供します。
家庭的な環境の中で、日常生活全般の支援を行うのが特徴です。
介護福祉士の主な業務内容は以下のとおりです。
- 食事の準備と介助:入居者と一緒に調理したり、個々の状態に合わせた食事介助を行います。
- 入浴・排泄の介助:プライバシーに配慮しながら、安全で快適な介助を提供します。
- 服薬管理のサポート:医師の処方に基づき、服薬の管理や見守りを行います。
- レクリエーション活動の企画・実施:認知症の進行を遅らせるための活動を企画し、実施します。
「家庭的な雰囲気の中で働きたい…」と考える方には、グループホームは理想的な職場かもしれません。
グループホームでの介護福祉士の役割は、単なる身体介護にとどまらず、認知症の方の尊厳を守りながら、その人らしい生活を支援することにあります。
入居者一人ひとりの生活歴や好みを把握し、個別ケアを提供することで、認知症があっても安心して暮らせる環境づくりに貢献しています。
グループホームでは少人数制のため、入居者との信頼関係を深く築きやすく、一人ひとりの変化に気づきやすいという特徴があるでしょう。
介護福祉士として働く上で、認知症ケアの専門知識やコミュニケーション能力が特に求められる職場です。
>介護士から転職におすすめの転職先を見る
障がい者施設での介護
障がい者施設での介護福祉士の役割は、利用者一人ひとりの尊厳を守りながら、自立した生活を支援することです。
障がい者施設には、身体障がい、知的障がい、精神障がいなど、様々な障がいを持つ方が利用されています。
介護福祉士は、それぞれの障がい特性を理解し、個別のニーズに合わせた支援を行います。
「障がいのある方の支援は難しそう…」と感じる方もいるかもしれませんが、利用者の小さな成長や笑顔に大きなやりがいを感じられる職場です。
障がい者施設での主な業務内容は以下の通りです。
- 日常生活支援:食事、入浴、排泄などの基本的な生活動作の介助を行います。
- 社会参加支援:外出支援や地域活動への参加をサポートし、社会とのつながりを維持できるよう援助します。
- コミュニケーション支援:言語障がいや聴覚障がいがある方には、適切なコミュニケーション方法を工夫します。
- 生活訓練:日常生活スキルの向上を目指した訓練プログラムを実施し、できる限り自立した生活を送れるよう支援します。
障がい者施設では、医療職や相談支援専門員など多職種と連携しながら、チームで利用者を支えることが重要となっています。
介護福祉士の専門知識と技術は、障がい者支援の現場でも大いに活かせるのです。
病院での介護福祉士の役割
病院での介護福祉士の役割は、医療チームの一員として患者の生活支援を担うことです。
医師や看護師が医療行為を行う中、介護福祉士は入院患者の日常生活全般をサポートします。
具体的な業務には以下のようなものがあります。
- 食事介助:患者さんの状態に合わせた食事の補助や見守りを行います。
- 入浴介助:身体状況に応じた安全な入浴をサポートします。
- 排泄介助:トイレ誘導やおむつ交換など、プライバシーに配慮した援助を行います。
- 移動・移乗介助:ベッドから車椅子への移乗など、安全な移動をサポートします。
「病院で働くなんて大変そう…」と思われるかもしれませんが、医療知識を学べる環境は介護福祉士としての視野を広げるメリットがあります。
病院では医療的ケアが必要な患者も多く、喀痰吸引や経管栄養などの特定行為を行うこともあるでしょう。
また、退院支援にも関わり、患者が自宅や施設に戻る際の生活環境調整も重要な役割です。
リハビリテーションスタッフと連携し、日常生活の中でのリハビリ効果を高める援助も行います。
病院内では多職種連携が不可欠で、カンファレンスへの参加や情報共有も日常的に行われます。
急性期病院、回復期リハビリテーション病院、療養型病院など、病院の種類によって業務内容は異なりますが、どの場面でも患者の尊厳を守る姿勢が求められるのは共通しています。
病院で働く介護福祉士は、医療と介護の橋渡し役として、患者の生活の質向上に貢献する重要な存在なのです。
介護福祉士の資格を活かせる職場

介護福祉士の資格は、介護施設以外でも多様な職場で活かすことができます。
例えば、生活相談員や福祉用具専門相談員、介護講師など、経験を積むことで専門性の高い職種へのキャリアアップも可能です。
以下で詳しく解説していきます。
資格を持つことで、直接介護だけでなく、相談業務や専門職としての道も広がるためです。
| 職種 | 仕事内容 |
|---|---|
| 生活相談員 | 利用者・家族の相談対応、サービス計画作成、関係機関との連携、施設運営・管理。 |
| 福祉用具専門相談員 | 利用者に適した福祉用具の選定・提案、使用方法説明、メンテナンス確認、利用者の自立支援。 |
| 介護講師 | 介護福祉士養成校や研修機関で指導、実践的な介護知識の伝授、指導者研修受講が必要。 |
生活相談員としての働き方
介護福祉士の資格を活かして生活相談員として働くことは、キャリアアップの選択肢として人気があります。
生活相談員は、利用者やその家族からの相談対応、サービス計画の作成、関係機関との連携などを担当する重要な役割です。
介護の現場経験を持つ介護福祉士は、利用者の状態を的確に把握できるため、生活相談員として高い評価を受けることが多いでしょう。
「介護の現場を知っているからこそ、利用者に最適なサービスを提案できる」と考える方も多いはずです。
生活相談員として働くには、介護福祉士の資格に加えて、一定の実務経験が求められる場合があります。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、デイサービスなど、様々な介護施設で生活相談員のポジションがあります。
相談業務だけでなく、施設の運営や管理業務に携わることもあり、将来的には施設長などの管理職へのステップアップも可能です。
コミュニケーション能力や問題解決能力が求められるため、人と接することが好きな介護福祉士に向いている職種といえるでしょう。
介護の知識と経験を活かしながら、より専門的な立場で利用者を支援できるのが生活相談員の魅力です。
福祉用具専門相談員の仕事内容
福祉用具専門相談員は、介護福祉士の資格を活かせる専門性の高い職種です。
主な業務は、利用者の身体状況や生活環境に合わせた適切な福祉用具の選定と提案を行うことです。
車いすやベッド、歩行器などの福祉用具について専門的な知識を持ち、利用者一人ひとりに最適な用具を提案します。
「どの福祉用具が自分に合っているのか分からない…」という利用者や家族の不安を解消するのも重要な役割でしょう。
福祉用具の使用方法の説明や定期的なメンテナンス確認も行います。
この仕事の魅力は、直接的な身体介護だけでなく、用具を通じて間接的に利用者の自立支援ができる点です。
介護福祉士としての経験を活かしながら、より専門的な知識を身につけられるキャリアパスといえます。
福祉用具専門相談員として働くには、「福祉用具専門相談員指定講習会」の受講が必要です。
介護福祉士の資格を持っていると、この講習会の一部科目が免除されるメリットがあります。
福祉用具貸与事業所や販売店、介護ショップなどで活躍できる職種として、介護福祉士のキャリアの幅を広げる選択肢となっています。
介護講師としてのキャリア
介護福祉士の知識と経験を活かして、介護講師として活躍する道もあります。
介護の現場経験があるからこそ伝えられる実践的な知識は、次世代の介護人材育成に大きく貢献できるでしょう。
介護講師として働ける主な場所は次のとおりです。
- 介護福祉士養成校:実技指導や専門知識の講義を担当し、将来の介護福祉士を育成します。
- 介護職員初任者研修機関:介護の基礎知識から実技まで、初心者向けの研修を行います。
- 実務者研修施設:介護福祉士を目指す人向けに、より専門的な内容を教えます。
「自分の経験が誰かの役に立つなんて考えたこともなかった…」と思う方も多いかもしれません。
講師になるためには、一定の実務経験に加え、指導者研修の受講が必要な場合があります。
教える立場になることで自分の知識も整理され、さらなるスキルアップにつながることが多いです。
また、現場勤務と比較して身体的負担が少なく、長く介護業界で活躍したい方にも適した選択肢となっています。
介護講師としてのキャリアは、現場での経験を社会に還元する貴重な機会となるのです。
すぐに介護福祉士が転職をしたいなら転職サイトがおすすめ!
マイナビ介護職|大手だからこそ高収入求人も多数

「マイナビ介護職」は大手人材会社の「マイナビ」が運営するサービスで、大手だからこその求人をトップクラスで保有しています。
マイナビ介護職では資格がなくても利用できますが、以下の資格を保持していることでよりあなたの条件にぴったりのお仕事を見つけることができるでしょう。
はじめての転職にも強い転職サイトで、以下の方におすすめです。
※株式会社マイナビのプロモーションを含みます
介護福祉士が転職を考える際のポイント
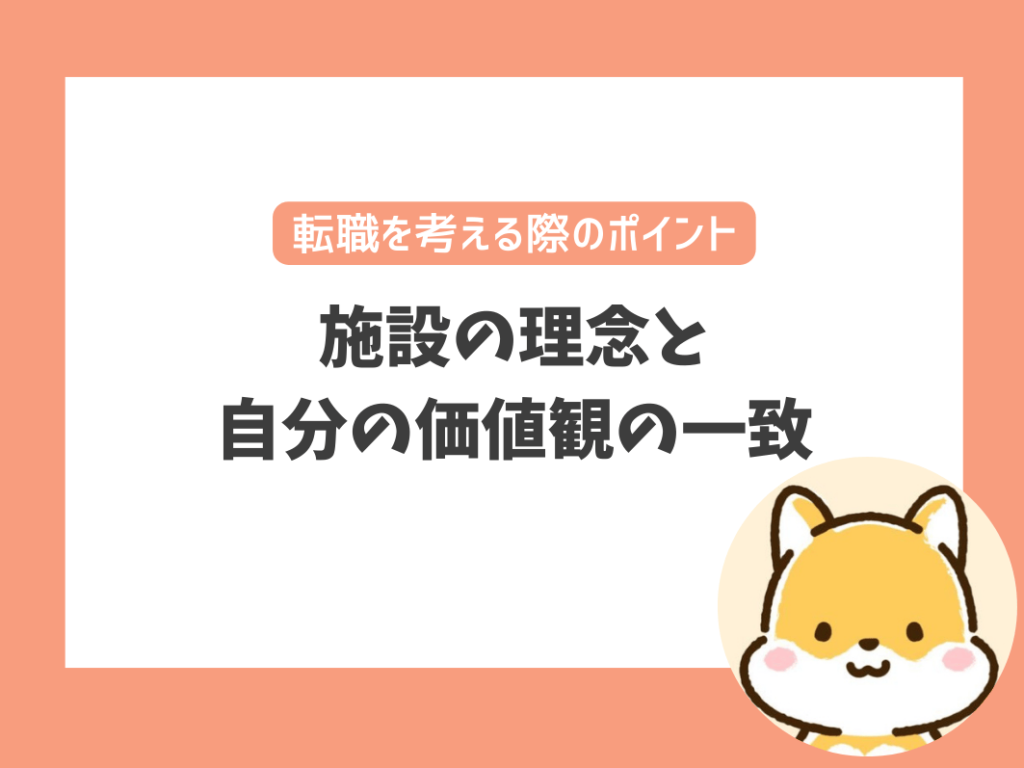
介護福祉士が転職を検討する際は、自分に合った職場を見つけるための重要なポイントがいくつかあります。
転職先選びで失敗しないためには、給与条件だけでなく、職場環境や将来性、自分の価値観との一致度など、多角的な視点での検討が必要です。
以下で詳しく解説していきます。
夜勤の有無、利用者層、施設の理念などは日々の仕事の満足度に大きく影響します。
| 選択基準 | 説明 |
|---|---|
| 施設の理念と自分の価値観 | 自分の介護に対する価値観と施設の理念が一致しているか確認。実際の現場の方針やスタッフの声をチェック。 |
| 仕事内容と日々の業務 | 実際の業務内容、夜勤の有無、身体的負担、業務マニュアルの整備状況などを確認。職場見学や体験入職で体感する。 |
| 給料や福利厚生 | 給与水準、賞与、有給休暇取得状況、夜勤手当、社会保険完備など。転職前に十分な確認を行うこと。 |
| 研修制度とキャリアアップ | 研修内容や期間、外部研修支援、資格取得支援、キャリアパスの明確さを確認。成長機会の提供を重視。 |
| 職場の人間関係 | スタッフ同士のコミュニケーション、管理者の対応、離職率など。職場見学や実際のスタッフの声を参考にする。 |
施設の理念と自分の価値観
介護福祉士が転職を考える際、施設の理念と自分の価値観の一致は最も重要な選択基準の一つです。
理念が自分の価値観と合致している職場では、やりがいを感じながら長く働き続けることができます。
「利用者の自立支援を大切にしたい」「その人らしい生活を支えたい」という思いがあるなら、同じ価値観を持つ施設を選ぶことが大切でしょう。
転職前には必ず施設のホームページや求人情報で理念を確認し、可能であれば見学や面接で具体的な取り組みについて質問することをおすすめします。
「この施設の方針には共感できるけど、実際の現場ではどうなんだろう…」と不安に思うこともあるかもしれません。
そのような場合は、実際に働いている介護福祉士の声を聞ける職場見学や、施設の行事に参加してみるのも良い方法です。
理念と実際の介護現場の姿勢に大きな乖離がある施設では、介護福祉士としてのやりがいを感じにくくなる可能性があります。
自分の大切にしたい介護の価値観と施設の理念が一致していれば、日々の業務にも意欲的に取り組むことができるでしょう。
仕事内容と日々の業務内容
介護福祉士として転職を考える際、実際の仕事内容や日々の業務を事前に把握することが重要です。
施設や事業所によって業務内容は大きく異なります。
例えば特別養護老人ホームでは、食事・入浴・排泄などの直接介助が中心となりますが、デイサービスでは送迎やレクリエーション運営も重要な業務になります。
「この施設では具体的にどのような業務を担当することになりますか?」と面接時に質問してみるとよいでしょう。
また、夜勤の有無や回数、記録作業の量、身体的負担の程度なども確認すべきポイントです。
「思っていた仕事と違った…」とならないよう、可能であれば職場見学や体験入職を活用して実際の業務を体感することをおすすめします。
業務マニュアルの整備状況も重要な判断材料になります。
明確な業務手順が示されていると、新しい職場でもスムーズに仕事を覚えられるでしょう。
給料や福利厚生の確認
介護福祉士の転職を考える際、給料や福利厚生は生活の安定に直結する重要な要素です。
施設タイプや地域によって給与水準は異なりますが、一般的に介護福祉士の平均月給は25万円前後となっています。
「給料は高いけど、休みが少なくて体を壊してしまった…」という話もよく耳にします。
給与だけでなく、以下の福利厚生も必ず確認しましょう。
- 賞与の回数と金額:多くの施設では年2回の賞与があり、月給の2〜4ヶ月分が相場です。
- 夜勤手当や資格手当:夜勤手当は1回あたり5,000〜10,000円が一般的で、資格手当も月数千円〜2万円程度支給される場合があります。
- 有給休暇の取得率:実際に有給休暇が取れる職場環境かどうかは働きやすさに直結します。
- 社会保険の加入状況:健康保険や厚生年金などの社会保険完備は安心して働くための基本条件です。
転職サイトの情報だけでなく、可能であれば実際に働いている方の口コミも参考にすると良いでしょう。
給与や福利厚生の条件は長く働き続けるために非常に重要な要素なので、面接時に遠慮なく質問することをおすすめします。
研修制度とキャリアアップの機会
介護福祉士のキャリアアップには、充実した研修制度がある職場を選ぶことが重要です。
良質な研修制度がある職場では、最新の介護技術や知識を継続的に学べるため、専門性を高めることができます。
「この施設に入職したら、どんな成長機会があるのだろう…」と考える方も多いでしょう。
転職先を検討する際は、以下の研修制度やキャリアアップ機会をチェックしましょう。
- 新人研修の内容と期間:入職後すぐに受ける研修の質は、その後の業務への適応に大きく影響します。
- 定期的な内部研修の有無:最新の介護技術や知識を学べる機会が定期的にあるかどうかは重要なポイントです。
- 外部研修への参加支援:外部セミナーや講習会への参加費用を施設が負担してくれるかも確認しましょう。
- 資格取得支援制度:ケアマネジャーや認知症ケア専門士などの上位資格取得をサポートする制度があると心強いです。
- キャリアパスの明確さ:将来的にどのようなポジションを目指せるのか、昇進の道筋が明確になっているかを確認します。
研修制度が充実している職場は、介護福祉士としての専門性を高め、長期的なキャリア形成につながります。
職場の人間関係の重要性
介護福祉士の職場選びで最も見落とされがちなのが「人間関係」の重要性です。
どんなに給料が良くても、職場の雰囲気が合わなければ長く働き続けることは難しいでしょう。
「人間関係が良好な職場なら、多少の忙しさも乗り越えられるのに…」と感じている方も多いはずです。
介護の現場は常にチームワークが求められる環境です。
職場見学や面接時には、スタッフ同士のコミュニケーションの様子や、管理者の対応を注意深く観察することが大切です。
また、離職率の高さは職場環境を反映していることが多いため、事前に確認しておくと良いでしょう。
- 職員の表情や会話の雰囲気
- 管理者とスタッフの関係性
- 新人教育の体制や相談しやすい環境があるか
転職前に可能であれば、実際に働いている方の声を聞くことも効果的な方法です。
良好な人間関係がある職場は、介護の質も高まり、あなた自身の成長にもつながります。
介護福祉士に関するよくある質問
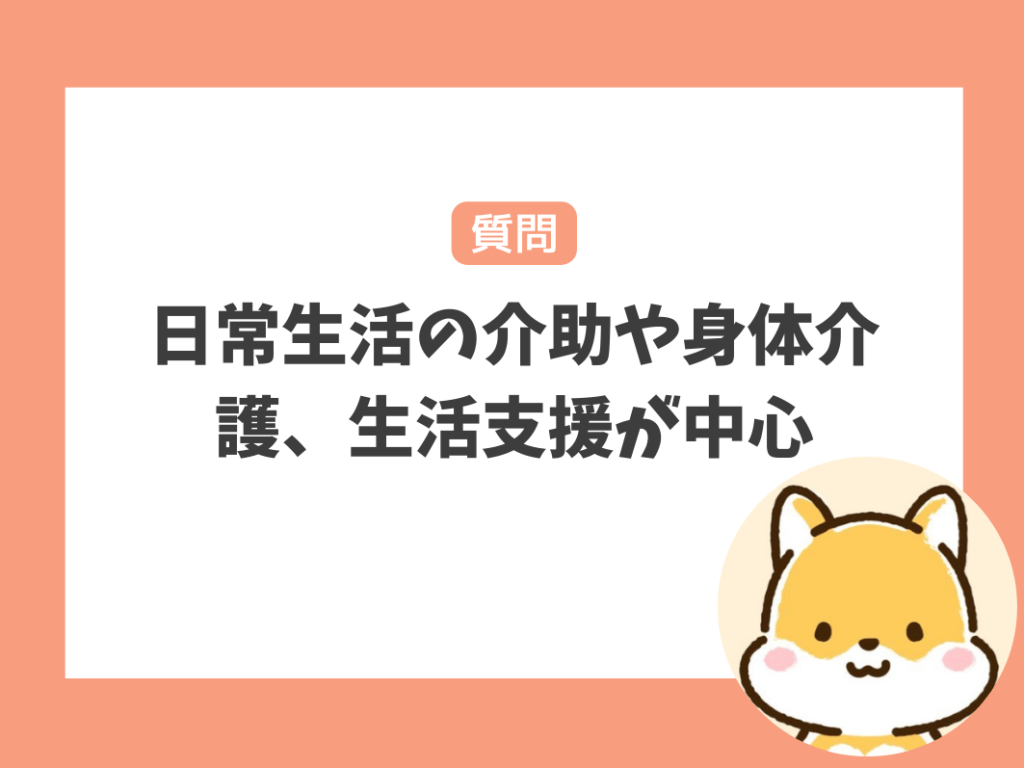
介護福祉士に関する疑問や不安は、キャリアを考える上で重要なポイントです。
多くの方が「どんな仕事をするの?」「将来性はあるの?」といった基本的な質問から、「資格取得の方法は?」といった具体的な疑問まで持っています。
以下で詳しく解説していきます。
こうした質問に答えることで、介護福祉士という職業への理解が深まり、キャリア選択の参考になるでしょう。
介護福祉士の仕事内容は?
介護福祉士の基本的な仕事内容は、日常生活の介助や身体介護、生活支援が中心です。
具体的には、食事・入浴・排泄などの身体介護から、掃除や洗濯といった生活援助まで幅広い業務を担当します。
また、利用者の心身状態を観察し、介護記録の作成や介護計画への参画も重要な役割です。
「介護の専門家として働くのは大変そう…」と感じる方もいるでしょう。
しかし、介護福祉士は単なる介助者ではなく、利用者の自立支援を目指すプロフェッショナルです。
医療職との連携や家族への助言など、チームケアの一員として活躍する機会も多くあります。
介護福祉士は資格を活かして、利用者一人ひとりの尊厳を守りながら、その人らしい生活を支える重要な存在なのです。
介護福祉士としてのキャリアパス
介護福祉士のキャリアパスは多岐にわたり、経験を積むことでさまざまな道が開けます。
まず基本的なキャリアステップとしては、一般職から主任・リーダー、そして管理職へと昇進していくルートがあります。
現場での経験を活かして、ケアマネジャー(介護支援専門員)の資格を取得する道も人気です。
「介護の現場で働き続けたいけれど、もう少しステップアップしたい…」と考える方も多いでしょう。
そんな方には、専門性を高める認定介護福祉士や、サービス提供責任者などの道もあります。
また、介護福祉士の知識を活かして、福祉用具専門相談員や生活相談員へとキャリアチェンジする選択肢もあります。
教育分野に興味がある方は、介護職員初任者研修の講師や介護福祉士養成校の教員として活躍することも可能です。
さらに、施設長や事業所管理者を目指したり、独立して介護事業を立ち上げたりする道もあります。
- 現場でのキャリアアップ:主任・リーダー→フロア責任者→施設長など、現場経験を活かして管理職を目指す道
- 専門資格の取得によるキャリア展開:ケアマネジャー、認定介護福祉士、社会福祉士など関連資格を取得して活躍の場を広げる方法
介護福祉士としてのキャリアは、自分の適性や目標に合わせて柔軟に設計できることが大きな魅力です。
介護福祉士の資格取得方法
介護福祉士の資格を取得するには、主に3つの方法があります。
1つ目は、介護福祉士養成施設を卒業する方法です。
2つ目は、実務経験ルートで、3年以上の実務経験を積んだ後に国家試験を受験する方法です。
3つ目は、福祉系高校を卒業して国家試験を受験する方法です。
「資格取得にはどのルートが良いのだろう…」と迷う方も多いでしょう。
実務経験ルートを選ぶ場合は、介護職員初任者研修や実務者研修の受講が必要になります。
養成施設ルートでは、2年間の専門的な学習を経て卒業すると国家試験の受験資格が得られます。
福祉系高校ルートは、高校在学中から専門的な知識を学べる点がメリットです。
いずれの方法でも、最終的には国家試験に合格することが資格取得の条件となります。
試験は例年1月に実施され、合格率は約70%前後で推移しています。
介護福祉士の資格は、様々な介護現場で活躍するための確かな第一歩となるでしょう。
まとめ:介護福祉士が活躍できる場所は多様
今回は、介護福祉士の働き先について知りたい方に向けて、
- 介護福祉士が働ける施設やサービスの種類
- 介護福祉士の活躍の場の広がり
- 介護福祉士の働き方の選択肢
上記について、解説してきました。
介護福祉士は高齢者施設だけでなく、障害者支援施設や医療機関、在宅サービスなど多様な場所で活躍できます。
それぞれの職場には特徴があり、自分の希望や適性に合った働き方を選ぶことが可能です。
これまで培ってきた介護の知識や技術は、どの現場でも必ず役立つものです。
あなたの「人を支えたい」という思いは、様々な介護の現場で必要とされています。
介護福祉士の資格を持つあなたには、多くの選択肢があることを忘れないでください。
ぜひ自分に合った職場を見つけて、介護のプロフェッショナルとして活躍してみてはいかがでしょうか。
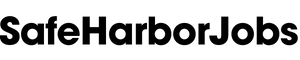

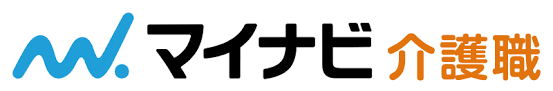

 レバウェル
レバウェル ブレイブ介護士
ブレイブ介護士 スタッフサービス・メディカル
スタッフサービス・メディカル レバウェル介護
レバウェル介護 ジョブメドレー
ジョブメドレー 介護ワーカー
介護ワーカー